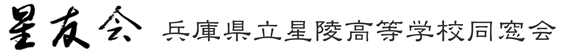1990年4月に星陵に入学し、93年3月に卒業した、鶴谷(つるや)と申します。バッジの色は黄色でした。私たち45回生は、1年の1学期は旧校舎で学びました。黒ずんだコンクリートの塊のまわりに桜をはべらせた眺めは一幅の絵でした。1年の2学期から仮校舎へ移り、2年の終わりまで過ごしました。かつて星陵の北側に神戸商科大学(現・兵庫県立大学)があり、それが西区の学園都市へ移転して空き家になっていた所へ入ったわけです。旧校舎を解体作業中の鳶職が、屋上の縁をスタスタ歩いているのを見上げて、落ちやしないかとヒヤヒヤしました。そして3年になると真新しい新校舎へ。ただ、生徒の手による掃除がいい加減なため、あっという間にホコリまみれになったのが面白かった。窓の外を眺めれば、建設中の明石海峡大橋の主塔がぐんぐん高く伸びていった頃です。旧・仮・新の3つの校舎をすべて体験したのは45回生だけです。体育館や武道場は卒業まで変わりませんでしたが、今は、それらも建て替わったのでしょうか?
入学当初、教室の後ろの黒板には「男はやっぱりラグビー部よね!」などと、運動部の勧誘文句が色とりどりのチョークでびっしり書き込まれていました。当時はバブル経済のさなかでした。「一杯のかけそば」が社会現象になった次の年です。高級車「シーマ」が電話1本で飛ぶように売れていると話題になりました。そう言えば、3年の時に星陵OBの都市銀行の副頭取さんによる講演会があり、副頭取さんは講演の間じゅう、「バブル」と言うべきところを「バルブ」と言い続け、生徒たちがクスクス笑っていました。初夏の星陵祭の思い出を少し。1年の時、隣のクラスが「24時間、戦えますか」「ジャパニーズビジネスマーン」と、当時しきりにテレビで流れていた栄養ドリンクのCMソングを歌い、喝采を浴びました。上級生たちによるフィーリングカップルという出し物には、ちょっと大人びた感じの男女が黒いボードを挟んで座り、見物客が廊下まであふれるにぎわいでした。3年の時に講堂で演劇部の舞台を鑑賞し、立ち上がれないほど感動しました。滅びゆく世界の片隅で、シェルターのような場所にこもって語り合う若者たちの絶望を描いたストーリーだった記憶があります。観客は、わずか数人でした。これほど素晴らしいのに、もったいないと思ったものです。
星陵生活も終わりに近づいた3年の3学期の体育の授業で、ソフトボールをした時です。運動神経の鈍い私ですが、なぜか大活躍しました。打てば外野の頭を越える大飛球を連発し、センターを守っては前へ横へと走り回って好捕を繰り返しました。ちょっと情けないですが、これが私の星陵時代の最高の晴れ舞台です。勉強は思うに任せず、個人的な事情から2年の晩秋に部活をやめてからはふさぎ込む日が長く続いていました。
九州の熊本大学で4年間を過ごし、97年春に神戸に戻って食品卸会社へ就職しました。そこで総務や営業をして働きました。通勤の電車で新聞を読むうちに、これを書く仕事をしたくなっていきました。学術的なレベルにはほど遠いとはいえ、政治経済や論壇、現代史に興味がありました。そこで、勤め先には内緒で毎日や朝日などの記者の試験を何度も受けましたが、落ち続けました。ようやく合格したのは、目の前の食品を売ることに本気になり、営業先に可愛がられて仕事が楽しいと思い始めた頃でした。その時、星陵の3年の時の担任が口癖のようにおっしゃっていた「ポストでベスト。今あるポストでベストを尽くしてこそ、初めて次のステップへ進める」という言葉を思い出し、その通りだとつくづく実感しました。
長田に行けずに星陵、旧帝大へ行けずに熊大、志望の企業(某JR)に落ちて中小企業に拾ってもらい……と、今思えばごく些細なこととはいえ、私は節目ごとに劣等感を友として歩んでいました。新聞記者になる目標は何とかかなえました。2002年春、私より5歳若い新卒の同期たちと一緒に毎日新聞社の入社式に臨みました。初任地は岡山で、初めて命じられた取材は、たくさんの鯉のぼりが泳ぐイベントでした。車を運転して駐車場に停め、肩からカメラ(当時はニコンF4)をぶら下げて歩き出した瞬間の、ふわふわと雲を踏むような靴底の感触を今も覚えています。
あこがれの新聞記者でしたが、とても泥臭く、小心者の私にとってはなかなか大変でした。駆け出しは必ず事件事故の担当、いわゆるサツ回りです。厳密に言うと、まずはサツ回りの先輩の手足として現場を走り回ります。朝や夜に取材対象者が自宅を出入りするタイミングを狙って接触することもしばしばあります。ライバル紙に特ダネを抜かれると、午前3時に枕元の携帯電話が鳴って叩き起こされ、未明から事実確認に走ります。知識や文章力は当面は必要ありません。土下座もいとわぬ腰の軽さと低さが大事です。そして、人間が大好きで、芸者さんのような愛嬌があれば、なおいい。もちろん、体力も。
修羅場となるのは、嫌がる人の元へ押しかけて、彼らにとって不名誉な話を聞き出したり、死者の顔写真を提供してもらうケースです。混乱と怒りと悲しみのるつぼにいる人たちですから、こちらも心が痛みます。警察官や消防士や医者や弁護士と違って、記者はその場で彼らを助けることはできません。蛇蝎のごとく嫌われ、水や塩をぶっかけられることもあります。岡山の次は京都へ転勤しました。まもなく尼崎市でJRの脱線事故が起き、私はすぐに駆り出されて遺族の取材に当たりました。前述のような日々が続きましたが、ある日の早朝、息子を亡くした父親が私の渡した名刺を見て電話をかけてきました。「今日、事故を起こした会社の社長がうちに謝罪に来ると言っている。あんた、うちに来て証人になってくれ。社長が言うことを見届けて、記事にしてくれ。約束したことを今後もずっと守らせるために」と言うのです。私は、ハッとしました。このお父さんが願っている役目は、記者にしかできないのだと教えられました。
私は30歳を過ぎてから急に、美術や音楽、舞台などに関心を持ち始めました。神社仏閣や大学などへの取材の機会にも恵まれ、08年春に大阪本社の学芸部へ転勤しました。文化部と称する新聞社が多いようですが、芸術や芸能を担当する部署です。配属されると、当時の学芸部長から「大阪毎日の学芸部の大先輩には、井上靖さんと山崎豊子さんがいる。しっかりやってくれ」と言われました。ご両人はかつて、ここで記者として働いたのです。ここ2年半ほどは、映画と放送を担当しています。年間300本くらい映画を見て、監督や俳優にインタビューしたり、映画評を書きます。テレビやラジオ番組も同様です。正直言って、学芸部に来るまで、新聞社にこんな担当があるとは知りませんでした。いきなり米倉涼子さんやブラックマヨネーズさんにお会いし、最近では香取慎吾さんや水谷豊さん、広末涼子さんなど。大きな役をたくさんオファーされている方に共通しているのは、皆さん、謙虚で親切なことです。これらの記事は、金曜または土曜の夕刊のエンタメのページに載ります。読者に楽しく読んでもらうために、まずは私自身が楽しもうと一生懸命です。
私は、新聞記者の存在意義は、突き詰めれば「平和と民主主義を守る」ことにあると考えています。今、日本では排外的で簡単な言葉、もっと言えば「子供の言葉」に民衆が手をたたく風潮があると思います。まさに右傾化で、戦前の昭和初期に近い。人間社会は複雑怪奇です。問題は簡単に解決しない。分かりやすくスカッとする言葉には、よくよく警戒すべきです。東日本大震災の後に流行した「絆」は、とても耳あたりがいいのですが、民衆の自由を縛って戦争に向かわせる小道具にもすぐになり得ます。自衛隊や警察の職務の尊さをPRする報道もいさかか過剰です。自戒を込めて。テレビの他愛ない町歩きの番組で、タレントの後ろに映っている人々の顔にことごとくモザイクがかかっているのを見て、背筋が寒くなりませんか? いったい、誰が何を守ろうとしているのでしょうか。映画やテレビはよく世を映していて、戦争賛美や国粋主義賛美としか思えない作品の一方で、反戦平和と表現の自由を希求するメッセージが込められた作品もたくさんあります。誰もが夢中になって楽しめるエンタメだからこそ、世を動かす力があると信じて、日々、取材しています。
私はこの夏で39歳になりました。精神年齢が幼いままのせいか、星陵を卒業して20年も経った実感はありません。当時、私の家は星陵から見て北側の本多聞の谷底にありました。家を出て、坂を登って下りて、もう一度登った先に星陵はありました。明石海峡を望む星陵は、「星陵温泉」と揶揄されることもある楽しい場所で、私にはいつもまぶし過ぎた。しかし、今こうして書く機会をいただいて気付いたのは、星陵の日々が頭の中のフィルムに何巻にもわたって鮮明に焼き付いていることです。1コマ映してみると、あれもこれも思い出して収集がつきません。そのフィルム倉庫には屈強な門番がいて、すぐに追い出されました。過ぎた日を甘く懐かしんでいる暇はないと叱られ、ちょっとほろ苦い気分で筆を置きます。先輩並びに同級生、後輩、そして在校生の皆様のご発展をお祈りしています。